石原慎太郎
TOKYO 革命
by 大下栄治
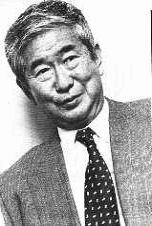
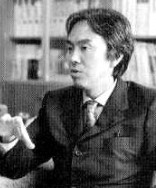
「あれだけ警告したのに・・・」
石原慎太郎は、平成七年、代議士を辞めようと決意したとき、長男の石原伸晃に電話をかけた。
「ちょっと相談があるんだ、遊びに来ないか」
平成七年四月七日だった。当時、伸晃も、衆議院東京四区選出の二回生議員だった。
伸晃は、どうしたのかといぶかった。
いままで父親の慎太郎が「相談がある」などといったことは、ただのいっぺんもなかったからだった。
「どうかしたの?」
「いや、演説の原稿ができたから、ちょっと見てくれ」
慎太郎は、一週間後の十四日、衆議院本会議場で、勤続二十五周年表彰の演説をする。その演説を伸晃に見てほしい、という。
おかしい、とは思ったが、父親が、なんの相談をしようとしているのかは、わからなかった。
伸晃は、演説の草稿を見せてもらった。
代議士を辞任すると書いてある。
思わず、父親にいった。「これは、まずいよ」
「なぜだ」
「だって、任期があるじゃない。任期まで勤めて辞めるのはいいけど、任期途中で辞めるのは、日本の政界の常識を覆すようなものだ。辞めるのは止した方がいいよ」
「どうすればいいと思う?」
伸晃は、これでは、あまりにも石原慎太郎すぎるじゃないか、と思った。があえてロにはしなかった。
別のいいかたをした。
「『今期をもちまして辞めさせていただきます』だったらいいんじゃないの」
が、慎太郎は、伸晃の意見を容れなかった。きっぱりといった。
「これが、おれの美学だ」
そういわれてしまえば、なにをいっても考えを変えさせることはできないと感じた。
<親父のばあい、常識よりも、美学が優先するんだろうな>
いろいろ話をしていると、父親の本心が痛いほどわかった。
自民党が下野したとき、橋本龍太郎政調会長の肝煎りで、直々に「自民党再生のための提言」をまとめた。
石原慎太郎が率いる小林興起、衛藤晟一など「黎明の会」の議員の他、自民党の正式機関の労力を結集させて、慎太郎が中心となって、自民党の正式提言をつくった。
慎太郎は、党の外交調査会の会長を務めたこともあり、これまで提言づくりに関わったことはある。しかし、それは事件があったときどうするかというレべルであり、しょせん官僚が書いた文章にすぎない慎太郎自身が、政治家として自分で手を入れて書いた提言は伸晃の知るかぎり、これが初めてのことではなかったか。
「おれは、ノーギャラであれだけのものを書いたのは初めてだ。あんなに警告をあたえたのにだよ。レスポンス(反応)が悪すぎるよ」
慎太郎は、明らかに自民党執行部の鈍感を嘆いていた。
伸晃も、よくできた提言だと感心していた。思い入れの強さは理解できた。
慎太郎は、その後の自民党の凋落ぶりと国民からの愛想づかされぶりを、肌で感じてひどく落胆したことだろう。
「笛吹けど、太鼓叩けど踊らずだ」みたいなことをいった。
4年ごとに出馬要請が
「このあと、自分でものを創造できるのはあとよくて七五才までだ。この限られたなかで、おれは仕事に集中したい」
いわれてみれば、政治家と作家というのは、両立しないと伸晃は思っていた。文学者というには内面の世界を創造する仕事。それに反して、政治家は外に向かってする仕事である。相容れない部分は多いはずだ。
政治家という仕事は、石原慎太郎くらいのベテランになっても、けっこう雑用が多いものだ、と伸晃はいう。
後援者の親類縁者の結婚式の出席。国会議員として、国会本会議で重要法案のときは、かならず席に着いていないといけない。腰を痛めている慎太郎は、議会で長い間座っていることは大嫌いであった。国会以外でも、朝早くからの会合は、大の苦手であった。朝八時からの、ホテルでの朝食会を兼ねた勉強会などというときは、いつもそのホテルに部屋を取って泊まりこみでなければならなかった。ナイン・トゥ・ファイブの仕事には、まるで弱かった。逆に作家生活の習慣で、夜にはめっぽう強かった。そのうえ、政治家・石原慎太郎として赤坂の事務所でものを書くのと、逗子の自宅で、海を見ながらものを書くのとでは、まったくちがうことだろう。
伸晃は、政治家・石原慎太郎ではなく、もともとの出発点であった文学者・石原慎太郎としての最後のエネルギーの燃暁という方向に父親が向かったことは、それはそれで結構なことだと賛成であった。そのうえ、政治家としてでなければ経験できなかったことなど、これからの作品に反映して、より石原慎太郎の世界を深く広くさせることができるにちがいない、ともおもっていた。そのためには、政治家と文学者の二足の革鞋を履きつづけることは時間的に無理だろうとも予測していた。
その後、政治家を辞任してから、石原慎太郎の文運は、勢い留まるところを知らなかった。石原裕次郎との思い出をつづった『弟』をはじめ、『宣戦布告「NO」と言える日本経済』などがベストセラーとなった。
<親父は、これで新しい生き甲斐ができた>
今回、伸晃は、都知事選に躍り出てきた父親の本意を、じつは最後の最後まで、外部に対して断定的に「出馬する」という形ではコメントできなかった。
出るといっておきながら、とつぜん前日になって止めてしまったりするからだった。
今回だけではなく、石原慎太郎の周辺は、昭和五十年に初めて美濃部亮吉都政に対抗して都知事選に出馬したとき以来、都知事選がやってくるたびにいつも騒然となる。
その騒動を、石原家では、四年に一度の「石原家の祭典」と称して、ちょっとしたギャグにしていた。
「また、言ってきたよ」
都知事選出馬要請があるたびに、慎太郎は伸晃や家族にそういって苦笑いをした。それだけ、慎太郎の存在が、都知事選のたびに、いつも気にかけられているという証左であった。そしてまんざらでもない顔をしていた。
しかし、伸晃が本気で石原慎太郎都知事を誕生させたかったときがあった。
告示の前日まで迷っていた
それが、一九九五年(平成七年)の都知事選のときだった。
自民党執行部から、伸晃に「お父さんに頼むことがあるかもしれない」との打診があった。
当時の幹事長は、今回の都知事選と同じく森喜朗幹事である。
伸晃は、政界入りしてからずっと旧清和会の安倍派−三塚派と属してきていた。そこで、森喜朗とは近かった。
自民党執行部は、石原信雄前官房副長官を都知事に担ぎだそうとしていた。
が、そのいっぽうで、軽口さえ叩いていた、という。
「石原信雄は、きっと止めるだろう。石原は石原でも、石原ちがいでいけるだろう」
そんな話をしながら、伸晃は、本気で慎太郎に勧めた。
「今度は、ぜひ出るべきだ」 父親の慎太郎は、まんざらでもない顔をしていた。
慎太郎は、そのとき、告示日の前日まで、出るか出ないか迷っていた。
そして、結論を出した。
慎太郎は、伸晃にこういって立候補を取り止めたのである。
「党に迷惑をかけるのはいかんから、やっぱりおれは止めるよ」
伸晃は、そんなのは方便だと思った。
<親父らしくもない言葉だ。なんでそんなエキスキューズをいうのか>
そして前内閣官房副長官の石原信雄が都知事選出馬を決心した。
伸晃や慎太郎の周辺は、憤慨した。
「ひとにものを頼んでおきながら、ほんとに馬鹿にした話だ」
石原信雄が、受けることを見越して、石原慎太郎に声をかけたようなフシも感じられた。都議会与党の公明党が、自民党の慎太郎擁立にまったく賛成しなかった、ともいわれる。
いまでも、たとえ石原信雄と戦っていたとしても、父親はいい勝負をしていたのではないか、と伸晃は思っている。
その石原信雄を破って、平成七年四月九日、青島幸男都知事が誕生した。その五日後、石原慎太郎は、衆議院議員を辞任するのである。
その前の鈴木俊一都知事再選のときにも、正式に自民党本部からの打診こそなかったものの、自民党の中から、「鈴木も磯村(尚徳・NHK解説委員)もだめだ。両方ともかつぎたくない。こんなのやっつけちゃいなさいよ」 という勧めはあった。当時の慎太郎は、その前の昭和六十三年に運輸大臣を経験、翌平成元年には、自民党総裁選にも出ている。その二年後の平成三年の話だ。
選ばれれば都知事を務めてもいい、という意志はあったのかもしれない、と伸晃は思っている。
石原慎太郎のもともとの姿勢は、「反権力」志向であろう。寄って立つところは、体制への批判である、と伸晃は思っている。書くものもそうだ。ところが、都知事になるということは、その逆の権力者となることでもある。
それなのに、今回、父親がなぜこれだけ、水を得た魚のように生き生きと仕事をしていられるのかというと、なんの未練もないからだ、と伸晃は思っている。 、
「長くやって権力者でいたいとか、そういうギラギラしたものがないからだ。ギラギラしたものがあると、もし国に話さずに、独自の政策を遂行するとすれば、国に意地悪をされると考え、手加減をするだろう。しかし、いまの父には、それがない。別に、それで辞めろっていわれれば、じゃあ辞めてやるよ、でも、おれ以外に誰がやるんだくらいのことをいうだろう。それにこれだけ世の中が厳しいときに親父がなったのも時代の巡り合わせがいいのかなとおもう。鈴木俊一都政の後期のバブルのころのように、貯金するだけとか物を造ったりするだけの都知事なら、父には合わなかったのではないだろうか」
都知事選を翌年にひかえた平成十年十二月、石原家では、いつものように四年に一度の"石原家の祭典”の話題で持切りだった。
2度目は負けられない
石原慎太郎は、青島幸男前都知事に対しては、特別のおもいがあった。青島は、昭和四十七年に参議員選挙に初めて出馬した同期だった。自分が断念した平成七年四月の都知事選で、慎太郎は、青島に一票を投じた。青島が新都知事になったとき、青島ならきっとなにか清新な政策をおこなってくれるものとの期待感があった。
しかし、平成十一年二月、青島が都知事選再選出馬を断念したとき、長男で衆議院議員の伸晃にははっきりといった。
期待してたのにな、青島君には・・・。でも、なにもできなかった」
ある意味で、今回、都知事選に出馬しょうと決心した背景には、そのことも大きな伏線となっているはずだ、と伸晃は見ている。
ただし、前回の平成七年の例もある。伸晃は、あまたの記者から取材を受け、石原慎太郎都知事選出馬ありなしや、質問を受けた。そのたびに、伸晃は答えた。
「父は絶対やるよ、とはいえない。ぼくは親父の性格を一番わかってるから、いえないよ」そして、本当に親しい記者だけには、平成七年のときの話をした。
「ぼくは、九五年のときには、親父に『やれやれ』ってずっと勧めてたんだ。本人もやる気だなって思ってた。そしたら、告示の前日になって『止めた』っていわれた。気が変わったら、すぐ止めちゃうひとだから、ぼくのところからはネタ出ないよ」
伸晃が迂闊に口にすると、その親しい記者の情報により、その記者の属している新聞は『出馬へ』と打ってしまう。と、その親しい記者のクビが飛ぶ。むしろ、その親しい記者を傷つけないために、そういう風に曖昧にいってきた。
それが、なぜ今回は出馬を決意したのだろうか。伸晃には、思うところがあった。「なんなのかな・・・。やはり青島さんには、それなりの何かあるんですよ、きっと。好き嫌いは別にして。やっぱり、あいつはなにか持ってるなっていう。だから、今回ならんだひとたちを見て、青島さんのときとちがい、なんだかドングリの背くらべみたいなおもいがあったのではないか。なにか物足りないっていう意味で。みなさん、青島さんがなったんだから、自分もできるみたいな錯覚があった。親父は、そういうものに対して、なにいってんの、という感じがあったんではないか。あくまでも、ぼくの推測ですが」
じっさいに、慎太郎は、立候補したときインタビューしたわたしにも、こうあかした。「すばらしい候補が出ているならわたしには出る幕はなかった。が、いってることは物足りないし、たぶん、都民も不満があるとおもう」
しかし、二度目の知事選では、敗けるわけにはいかない、慎重な姿勢も見せていたという。
そして、今回も慎太郎はまた、衆議院議員を辞任するときと同じく、伸晃に電話をしてきて同じセリフをロにしたのだつた。
「相談がある」
それが、平成十一年三月七日の夜だつた。
「自分はいろいろ考えた」
どうやら、二月から三月初めにかけ、、精力的に政界、言論界関係者に会って状況を分析していたようだ。
さらに、慎太郎は自著『国家なる幻影』をあらためて目にした。親友であったフィリピン元上院議員の故ベニグノ・アキノの最後を書いたくだりである。
慎太郎は、出馬前のインタビューでこう明かした「アキノが暗殺される前の晩、アキノと電話でしみじみと話した。おれは、アキノに、フィリピンに帰ることを引き止めた。しかし、アキノは聞かなかった。アキノは、暗殺されるかもしれない、ということをわかっていながら、あえて帰国したんだ」
慎太郎は、自著の中のアキノの最期に言及した文章を読んで、アキノの生き様、死に様を思い出して感動した、という。そこで、あらためて立候補を決心した。
翌三月八日、石原伸晃は、夕方の六時に会食の約束が入っていた。
八日の午後四時からの議員会館でのブリ−フイングで、伸晃は、記者相手にいった。
「今日の夜、父親から呼ばれている。そこでなにがあるかわかんないけど」
そういったとたん、伸晃は、報道陣からつけまわされる羽目になった。伸晃は、ちょっといやな予感がしていた。
そこで、会食の場所に入る前、伸晃の一挙手一投足をつけ狙っている報道カメラに、玄関口で釘を刺した。
「ここからは、それ無しネ。なにも、ネタ出ないから」
「わかりました」
伸晃は、いくら息子だからといっても、都知事選に引っかけてただの国会議員にすぎない自分を追いかけるのは、いいかげんにしてほしいと念押ししたつもりだった。ところが、あるテレビ局だけが、ずけずけと会食中の部屋にまでカメラを侵入させて石原伸晃を撮ろうとした。伸晃はさすがに声を荒らげた。
「ないだろ! それはッ」
なにかあるときは、かならずいう、と伝えてある。そんなに待てないか、と腹立たしかった。
執念深く追いかける報道陣を避け、部屋に入った伸晃に、同席していた人が同情した。
「大変ですね」
伸晃は、苦笑した。
「ええ、今度が二度目なんです。父から『相談あるから』なんていうのは。議員辞めるときに一度そういって呼ばれましてね」
かれらは、すぐに察した。
「あッ、もう、じゃ、あれですから、すぐに父上に会いに行ってください」
「申しわけない」
伸晃は、そういって断り、一時間半ほどでそこを出た。すぐに全日空ホテル三階にある中華料理店に向かった。石原慎太郎ほか何人かが待っているはずだ。仲間の数人が待機していた。
その仲間たちの前で、慎太郎が決意表明をした。
「自分は、今回、いろいろ考えた。東京都の財政は、思ったよりひどい。(知事を)やらざるをえないな」
全員、そうか、ついに決心したか、と気を引き締めた。伸晃は、さっそくあわただしく考えた。
<漏れてはいけない。どこか、記者会見場を探さなくっちゃな。>
用意周到と答えたのはウソ
その場で、政策骨子をつくるのはだれ、記者会見場を見つけるのはだれ、など各人の分担を決めた。伸晃は、すぐ自分の政策秘書に命じた。
「これとこれに、肉付けしといてくれ」
自分が考えていた都市政策、とくに東京政策で懸案である政策項目を秘書に伝え、それにボリュームをつけさせ、それを慎太郎に渡すつもりだった。環境問題など、かなり細かいところまで突っ込んで分析し、提言したものになっていた。いざというときに父親が困らないようにするためだった。
伸晃は、秘書が肉付けした政策を箇条書きにして、慎太郎に手渡した。
「だいたい、ここに書いてあるけど、いちおう、ぼくがブリ−フイングするから、その中で使えるとこを使ってよ」
父は、文章の専門家だから、伸晃のブリーフィングをもとに自分の言葉に変えて公約化するだろうと、安心していた。
<よしッ、もう敵はいない。今度こそ勝つ。だって、石原慎太郎以上に知名度ある人物なんていないもの>
伸晃は、慎太郎に伝えた。
ここまできたら、記者会見は、もうギリギリまで延ばして週末の金曜がいいよ」
なんの準備もしていない。時間はできるだけあった方がいい。すでに立候補を表明しているひとたちは、みなどれも似たりよったりで、特別眼をひくような話題はない、と報道陣も半ば退屈している。ここに「石原慎太郎出馬決意」というリードは、喉から手がでるほど打ちたいはずだ。伸晃は、日本テレビ政治部勤務の経験から逆の立揚で推測できるので、その落としどころをよくわかっていた。
しかし、記者会見をするとなれば、その前に事務所を確保しなければならない。それがおいそれと見つからない。
極秘で探さなくては漏れてしまう。制約ばかりで、なかなかはかどらなかったのだ。
それから間もなく、ちょうど伸晃の選挙区の知人がかつて持っていた土地に関する情報が入った。すでに知人は、その土地を手放していたが、頼めばなんとか借りられそうだという。やっとのことで事務所が見つかった。のちにマスコミの取材に「用意周到な準備で事務所を借りた」と答えていたが、まったくの嘘であった。そんなところに事務所用の土地が空いていたのがツイていた。
「明日の戦、わが身は無念」
さっそく三月十日水曜日に出馬記者会見をおこなった。千代田区内宰町にある日本プレスセンターでの会見には、三百人を超える報道陣が詰めかけた。
慎太郎は、「NOと言える東京」と名付け政策を掲げ、公約を訴えた。東京の主体性を強調したうえで、独自の債券市場構想を唱え、横田基地の返還を訴えた。おもいきった教育改革、環境改善のためのディーゼル車抑制政策、マイカーの規制を挙げた。さらには、こうした政策を実現するために、首都移転には激しい嫌悪感を露わにした。
「かつて金丸信氏が提唱し、ほとんどの国会議員が迎合した首都移転などナンセンスな構想です。江戸時代から今日にかけて成熟してきた首都東京を、いまさらいつどこに移して、いかなる新しい都市を建設できるというのでしょうか。それは歴史への反逆、いや冒涜とさえいえます」
慎太郎は、その二日前に「週刊文春」の取材に応え、あらかじめこう宣言し、みなぎる決意を剥き出しにしていた。
「東京が自立し、蘇るためには、都民自身が立ち上がらなければならない。教育にせよ、環境問題にせよ、あらゆる課題において、まず第一は、われわれが『他力本願』の姿勢を脱することです。『強い日本』を取りもどすためには、『強い東京』を作らなければならない。その戦いの場所が、今回の都知事選だと思います」
石原慎太郎は、出馬を決断するときの心境を、こう語った。
「ここまできたら、最後の御奉公だ」
石原の先祖は、武田の武士であった。武田家が潰れたあと、松山に抱えられたが、弓の名人であった。戦場でも、ずいぶん活躍をした。ある戦で敵を七人倒したということで七つ矢の家紋をもらった。
石原家の家訓は、「明日の戦、我が身は無念とこころうべし」というものである。明日の戦の結果、自分の命はあると思うな、つまり、死ぬつもりでやれということだ。
石原は、力をこめていった。
「まさに、その家訓が活きてきたな」
長男の進言に「いやオレは」
石原慎太郎の都知事当選が決まってから、石原伸晃は、都庁に四十回以上も通いつづけた。
四十回の都庁訪問では、父親慎太郎とは、たいてい昼食のときしか会えなかった。都知事は半端ではなく忙しい、そいうのは嘘ではない、と感じる。
伸晃が、まず最初に進言したことは、相手が石原慎太郎であってみれば、まさに正鵠を射ていたといえることだった。
「最初から一挙に細かい政策出してくと、息切れするからね。任期は四年ある。ひとつづつ着実にこなしていかないと。いろんなこというとネタ切れになるし、大風呂敷になっちゃう。みんな、石原慎太郎だ、なにかやってくれるじゃないかと期待して、票を入れてくれたひとが多い。あまり細かいことにこだわらず、細かい政策のことはブレーンにまかして、もっと大なところから都政を考えてよ」
東京都は、約二十万人の職員を抱える巨大な行政組織である。そのひとたちが協力してくれないと、いくら石原慎太郎だ、と粋がってもなにもできないのは目に見えている、といったつもりだった。
伸晃は、つづけていった。
「無理矢理やれっていったて、職員が納得したうえでなくちゃ、彼らも動かない。できるものからやっていった方がいいよ」
慎太郎は、少し反抗気味にいった。
「いや、おれはセッカチだから、思いついたことを全部やるんだ」
任期は、四年間だ。その間は、父親が、いくら「辞めたい」と思ってもやめられない。だから、息切れしないように、と釘を刺したつもりだったのだ。
父親は腰も痛めている。議会や知事執務室での椅子の生活は疲れるにちがいない。朝も弱い。だから、知事公館に住めとはいわないが、せめて都庁近くのホテルに部屋をとって、そこから通えばいいとも思う。が、それも拒否し、わざわざ五十分ないし五十五分はかかる自宅通勤を貫く。伸晃には考えられないことだが父親はやはり、自宅の方が落ち着くようだ。
<年とったのかな、家の方がのんぴりするのかもしれない。しかし、家にはお手伝いさんがいないから、母親は大変だろう>
伸晃は、しまいに疲れてつづかなくなるのではないか、と危ぷむ。が、父親かかりつけの整体師の先生が新宿にいる。その点、少し安心している。
知事になってからゴルフもできなくなった。運動しないから腰がすごく悪い」と不満を述べていた。腰が痛いからと椅子に座るのが大嫌いだった。知事になってますます椅子に座っている時間が長くなり、腰痛にはよくないはずだ。しかし、いざ都議会が始まると、慎太郎は、次々と斬新な政策をぶちあげた。持ち前の好奇心と政治への情熱が腰の痛みを忘れさせるようだ、と伸晃はおどろく。
慎太郎の政策のうち、伸晃がもっとも深く関わったのは、債券市場のことである。
伸晃が思っていたものとは若干形は変わったが、おもいのほか応募は多かった。三桁(百億円にとどけば御の字とおもっていたのが、七百億円近くにもなった。
伸晃は、中小企業の方々に直接金融というものを学んでもらえればいいと考えていたので、まずは成功と思った。
「中小企業は、銀行からの間接金融ではなく、直接、市場からお金を集めることもできるんだってことをわかってもらえればいい。日本の社会は、なんでもかんでもメインバンクを重要視する。世の中が変わるから、そういう意味で今回の債券市場は意味がある」
「銀行税」3%の理由は?
「外形標準課税」のことは、大蔵委員でもあった伸晃には得意分野のことで、父親には、よく話していた。
仲晃は、自分ならこうするというような試案も父親に渡してあった。
「これ、主税局長に渡しておけば何かの役に立つよ」
伸晃のレクチャーは、石原都知事の発言の中にしっかり活かされていた。
<親父、シェ−クスピアの『ペニスの商人』もちゃんと読んでたんじゃないかな。やっぱり金貸しのシャイロックが一番悪い。親父が銀行に憤ったのも、皮膚感覚だ>
慎太郎は、大蔵省は虫が好かなかった。
伸晃は、「外形標準課税」は、大塚主税局長と、家田課長という優秀な官僚が、慎太郎に「なんかいいのを考えろ」といわれ知恵を絞ってできたものだと思っている。
じつは、保険金社や電力会社や生保などは、すでに外形標準課税である。その税率は一・三%。そのため、今回の銀行税も当初の税率は二%だった。それで計算すると、都の税収増は六百億円から七百億円になる。
それを聞いた石原都知事は、憤慨した。
「けしからん、四桁にしろ」
それで、税率が三%になった。これは、ぁくまでも伸晃の推測である。
伸晃は、慎太郎とは親子なので、主張がイコールではなくとも、イコールだと思われがちだと感じている。
伸晃は、それゆえ、なるべくファイアウォール(防火壁)を設けている。
外形標準課税のときに、伸晃が「どういうことか都知事に事情を開いてくれ」と税調からいわれた、とよく新開にも書かれたが、そういう話は、党の方からは来ていない。伸晃は税調の幹事だから、税調のプロパーの議員たちと外形標準課税についての議論はするが、むしろ正式に発言するのは控えていた。
かろうじて、正式の税調の幹部会で、伸晃が最後に発言しようかと思って手を挙げた。すると、ベテランの議員たちからいわれた。
「石原君やめとけやめとけ。あんた黙ってたほうがすごみがあるから、やめとけ」
それで、正式な発言は控えた。みんなが好き勝手なことをいっていたので、よほど発言しようかとおもったが、いわなかった。そのため、いろんなひとから逆に訊かれた。
「ほんとは、あそこで何がいいたかったんですか」
仲晃は、今回の「外形標準課税」適用は、時代にとってみればいいこと、と評価している。
「銀行は税を納める能力がありますからね。とくに今回は、課税の対象を資金量五兆円以上に限ったでしょ。そりゃなかなか、一つの業界で一千百億円も税を取れるものってないですからね」
伸晃は、ある意味では、やはり石原慎太郎だからこそ、あそこまでできたのだろうとのおもいを抱いている。慎太郎自身がいっているように「ピーンポールを投げた」というのは、伸晃も同じおもいだ。
ディーゼル車を追放せよ!
石原慎太郎は、都知事選立候補宣言の公約で、具体的に述べている。
「私たちは単に乗る便利と自らの健康と寿命を本気でトレイドオフしなくてはならぬ時点にさしかかっていると思われます。現代の技術をもってすれば、わずかなコスト負担でディーゼルエンジンからの排気をガソリン車なみに抑制することは可能であり、新しい都の条例によって向こう三年の時限で以後排気ガス抑制の規格に合わぬ車の運行は禁止します」
その公約は、さっそく実行に移された。
知事就任四ケ月後の平成十一年八月二十七日、都庁第一本庁舎6階記者会見場での定例記者会見の席上、石原都知事は、発表した。
「東京都は『ディーゼル車NO作戦』を始めます。今日の時点からいずれかの時点で、ディーゼル車を東京からなんとか駆逐しようという作戦を展開いたしますが、ディーゼル車にはいろいろな問額がからんでいます。ディーゼル車が普及するひとつの要因は、軽油が同じ燃料でも優遇税制であるということで、それを是正していくことが必要です。コストの負担を誰がするかというと、】業者だけではなく、受益負担をしている都民もやはり被害者であり加害者であるという意識に立って、この問題に対処しなくてはならないと思います」
石原慎太郎は、ディーゼル車の悪影響は、ずっと前から、長男の伸晃にも、杉並区高井戸の伸晃の自宅にやってきたときに、何度か危機感を募らせていた。
「おまえの所の空気は、わるいなぁ。おれの所もひどいけど」
伸晃の所の空気が悪い。その対策を考える過程でディーゼル車規制を実現しなければいけない、と決心した、と伸晃は思っている。田園調布の慎太郎の家にも、川崎臨海工業地帯の工場の煤煙がかなり飛んでくる。「田園調布喘息」という言葉があるほどだ。
伸晃は、通産政務次官のときから環境問題の一環として、ディーゼル車の弊害を警告してきた。平成十一年八月から、東京都が「ディーゼル車NO作戦」を開始したのは、願ってもないことだった。
石野伸晃が、父親の石原慎太郎都知事にぜひとも実行してほしいのは、環状線の整備である。伸晃は、知事室に父親を訪問するたびに、東京都が抱えている問題点を指摘した。
「首都圏の交通渋滞を回避するには、土地収用法という法律をもっと活用すべきだ。ところが、日本は私有権が強すぎて、この法律が十分に機能していない。そのため、いつまでも外環道ができなくて、車の渋滞がひどい。タクシーの平均速度が十七キロなんて、そんな大都会ないよ。変な町だよ、東京ってとこは。大阪や名古屋などは、いちはやく道路の整備に取り組んだため、大阪の環状道路、名古屋の五十メートル道路などの見るぺき成果を上げてきてるじゃない」
伸晃は、東京だけは、他の大都市にくらべると、環状線の整備が遅れている、と痛感している。ひとつには、美濃部亮吉都知事の時代、美濃部都知事が、環境問題、公害問題に真剣に取り組む姿勢を明確にした結果、東京都かち公害を追放するという大前提により、ほとんどの公共事業をストップさせた。その負の遺産が、環状道路の不整備という結果を招来した。伸晃は、東京都選出の都市型議員としての責務から、町づくりをその政治ポリシーに掲げるプロパーである。その町づくりのプロパーとしての眼から東京都を見たとき、まさに東京は、“死に体”と化している。その東京を、根底からリニューアルしなくてはならない。
「早急に取りかかる」と宣言
伸晃の頭にあるのは、七代目東京市長の後藤新平のおこなった都市基盤の徹底整備である。後藤は、都心があり、その周囲に田園都市があり…という未来の都市づくりに真剣に取り組んでいた。その21世紀版を、父親には取り組んで欲しいとおもっている。いまのまま手を拱いていると、東京は、近い将来スラム街が出現してしまうだろうと読んでいる。
伸晃は、慎太郎にいった。
「生産年齢人口が減ってくるに連れ、移民を入れるなどの手もこうじられるね。一部屋に二十人もの外国人が雑居するようになる。都市計画法はあるのに、活かされていない。都市計画というより、街づくりのビジョンがない。一部の業者や個人的意図で、各地域を好き勝手にいじっている。土地収用法という法律があるにもかかわらずですよ。やっぱり、ここはひとつ都知事の権限をフルに発揮して、東京の都市計画をきちんとしてほしい」
伸晃は、早急に対策を立てて欲しい、といった。
「マスタープランがないんだ、東京には。環八だって、やっとできたけど、ノンストップの環状道路がないと駄目だよね。それに住居問題にしても、上海の浦東地区なんて、バラックのスラム街だったのが、みんなを無理矢理追い出しちゃったでしょ。こうして整備しておけば、地震があろうが、なにが起ころうが、びくともしない街に生まれ変われる」
仲晃は、こんな話を父親にしても興味がないのだろうな、と思いながら話した。すると、意外にも慎太郎は、伸晃の話に非常な興味を抱いた。
「もっと詳しく話してくれ」
伸晃は、挑発するようにいった。
「東京都には、まがりなりにも都市計画局というのがあるんだから、ちゃんとマスタープランつくらせてやらせてよ」
すると、慎太郎は憮然とした表情で突っ撥ねた。
「役人なんかに作らせたらだめだ。早急に建築界の知っている人間を集めてとりかかる」
「そうだよ。やってもらわないと、おっかなくて暮らせないから」
東京二十三区の特別区にしても、区ごとにまったく生活環境がちがいすぎる。だから、伸晃が思うには、これらを百万都市に括り替えて、新たな都市づくりをしてほしいくらいである。
(文中敬称略)
