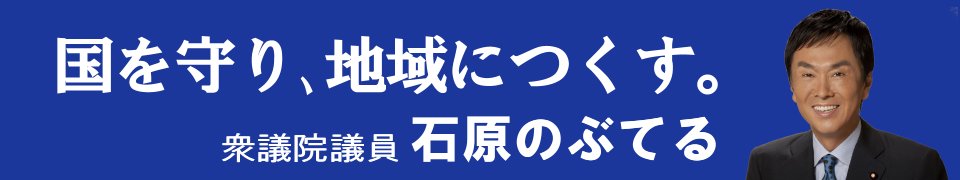平成25年10月10日「水銀に関する水俣条約」(the Minamata Convention on Mercury)が、140の国の代表の賛成を得て採択されました。この条約は水銀汚染による健康被害を防ぐための地球規模の取り組みです。輸出入による水銀の使い方を限定すること、水銀の大気・水・土壌への排出を減らすこと、水銀やその化合物、水銀廃棄物が環境に害を与えない様に管理すること、途上国への技術資金援助、等を定めています。
Continue reading
Category Archives: 環境省
ツバル訪問
南太平洋の島国、ツバルを訪問しました。
まずイタレリ総督とお会いしました。ツバル国王はイギリス王室が兼ねているため、総督はこの島国のシンボル的な存在です。気候変動の影響が世界中で最も大きいと言われるこの小さな島国で、日本の支援は非常に感謝されています。イタレリ総督からも、実際に日本の協力がどのようにこの国で活かされているか、しっかりと見て下さい、と言って頂きました。
省エネへの取組み
地球温暖化を防ぐ観点から、化石燃料の使用をいかに抑えるかは、大変重要です。先週は都内で、重点的に省エネ問題に取り組みました。

省エネの第一歩はまず国民の皆様にご理解とご協力を頂くことです。そのため環境省では、「貞子ときっとク~ル計画」を推進しています。※貞子ときっとク~ル計画詳細はコチラ

また、もう一つ重要な事は自然環境を上手く利用することです。風力・水力・地熱・太陽光等、自然エネルギーを使って発電することも必要ですが、自然のエネルギーそのものを役立てることも大切な取り組みです。東京・京橋で、世界最先端の省エネビルを視察しました。 Continue reading
対馬ヤマネコ・八丁原地熱発電所訪問
先週は、長崎県対馬でツシマヤマネコとの共存の取り組みを、大分県玖珠郡九重町では、日本最大の地熱発電所を視察しました。

対馬はツシマヤマネコのふるさと。ツシマヤマネコは現在地球上で対馬に100匹しかいない絶滅危惧種です。私達が積極的に保護していかなければ、ツシマヤマネコが地球上から消えてしまう日が来るかも知れません。自然環境を守っていくことは、手間や時間もかかり、短期的な利益に結びつきにくいものです。しかし長い目で見れば、人間にとっても大切です。 Continue reading
欧州視察
フィンランド・アイスランド・フランスの3カ国に行ってきました。

フィンランドではオンカロ放射能廃棄物最終処分場候補地の視察に行ってきました。世界的にも最終処分場の候補地が決まっている国はフィンランドとスウェーデンの二カ国しかありません。もちろん、処分場がなければ原発を廃炉にすることもできません。日本のエネルギー政策を考えていく上で、オンカロは大変重要な示唆を与えてくれる施設です。


アイスランドでは、ステファンソン駐日大使のお招きで、世界最大のヘトリスヘイジ地熱発電所、環境との調和を第一に作られたネシャヴァトレル地熱発電所を視察しました。実はアイスランドの地熱発電を支えているのは日本の技術です。日本とアイスランドは、自前の資源を持たない島国として共通の課題を沢山持っています。今回、アンナドッティル産業大臣、ヨーハンソン環境大臣、クリスチャンスドッティル内務大臣と会談し、お互いの経験や技術、ノウハウを共有し今後も協力していくことを確認しました。


フランスでは、マルタン環境大臣と会談しました。フランスは2015年のCOP21の議長国と目されており、環境に対するこれからの世界的な取り組みの鍵を握る立場にあります。マルタン環境大臣は、大臣に就任してから、初めて外国のお客様とお会いするが、それが日本の石原大臣で大変嬉しい、と歓迎してくれました。環境問題は決して一国だけで解決することはできません。日仏で協力して国際世論を先導し、地球温暖化防止に取り組んでいきたいと思います。
以上3カ国をまわり、帰国しました。詳しくはfacebookをご覧ください。
「環境省情報セキュリティ対策本部」の設置について
今年1月の水銀条約交渉に関する環境省関係者のやりとりに関する情報が、インターネット上で外部からの閲覧が可能な状況が生じていました。
環境省内の情報管理については、繰り返し徹底を図ってきた中で、こうした事案が生じたことは甚だ遺憾です。民間の常識、霞ヶ関の非常識の案件です。
このため、本日午前、「環境省情報セキュリティ対策本部」を設置し、第一回の会議において、ハード・ソフトの両面から、情報管理の徹底について省内で総点検することを指示しました。

第一回の会議
お盆にはお墓参りに
沖縄科学技術大学院大学(OIST)
シンポジウムの会場となった沖縄科学技術大学院大学(OIST)を視察しました。
OISTは教員も学生も半分以上が外国人で、世界最先端の教育と研究は、全て英語。毎年約20名の学生が入学し、世界トップレベルの研究者による指導の下、様々な研究が行われています。
時間が限られていたため、研究成果のほんの一部しか見ることはできませんでしたが、日本が今後、世界に羽ばたいていくための種子が、着々と育っていることを実感しました。「様々な分野の研究者が、お互いにアイデアを出し合って研究を進めていく、そんな自由な環境を作りたい」 ドーファン学長の言葉には力がこもっていました。
島国まるごと支援
環境省の主催で、地球温暖化防止とサンゴ礁の保全について話し合う国際会議を開催しました。今回は主に世界中の島国に参加を呼びかけました。
島国は、資源に乏しいこと、水が不足しがちなこと、ごみ処理が難しいことなど、共通する課題を持っています。そして、日本はそれらの課題を克服してきた歴史と技術を持っています。ですから、私からはシンポジウムの冒頭、島国共通の課題を島国・日本が持っているノウハウで解決していく、「島国まるごと支援策」を提案し、参加者から賛同を頂きました。また、スピードの今井絵理子さん、涌井史郎先生との公開討論では、温暖化防止についての議論で盛り上がりました。